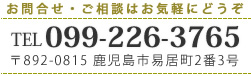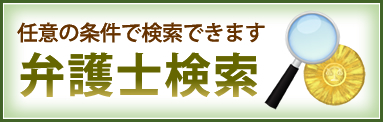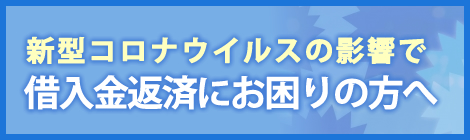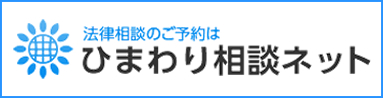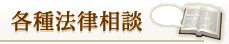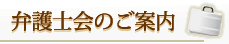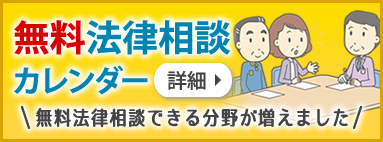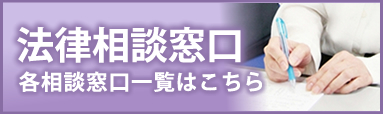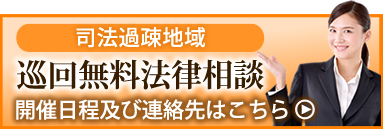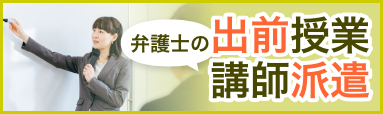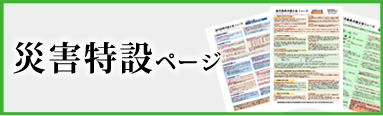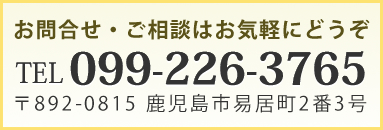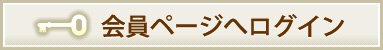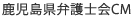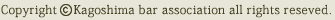決議・声明
離婚後の共同親権導入について慎重な検討を求める会長声明
2024年(令和6年)2月15日、法制審議会において、「家族法制の見直しに関する要綱」が採択され、同年3月8日には民法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)の閣議決定がなされた。改正法案は、同年4月16日に衆議院本会議において可決され、現在、参議院での審議が進められている。
しかし、改正法案については、特に離婚後の共同親権導入に関し以下のような問題点が残るため、今後さらなる慎重かつ十分な審議を尽くすこと及び、施行にあたって速やかに必要な措置を行うよう強く求める。
1 親権者の決定に関する問題点
(1) 虐待やDVの影響が続く危険性があること
現行法では、父母が離婚する際、協議又は裁判所の職権で父母のいずれかが未成年者の子の親権者に指定される(現行民法819条1項、2項、5項)。他方、改正法案では父母の「双方又は一方」が親権を行使する(改正法案819条)とし、離婚後の共同親権導入が検討されている。
改正法案においては、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」(改正法案819条7項1号)、「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動…を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が整わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」(同項2号)、「その他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」(同項柱書後段)は、裁判所は父母の一方を親権者と定めなければならない(同項柱書後段)と定められており、同項は虐待事案やDV事案を想定した条項であるとみることができる。
しかし、虐待やDVは密室で行われることが多く、特に非身体的暴力の場合には客観的証拠の収集は難しく、立証が困難である。そのため、実際には虐待やDVの事実があったとしても、裁判所が当該事実を看過し、共同親権を命じるおそれがある。共同親権とされてしまうと、離婚をしても加害者との接触を断ち切ることができないため、被害者や子の心身が危険にさらされ続けてしまう可能性がある。
(2) 親権者の判断基準が不明確であること
改正法案においては、父母の双方又は一方を親権者と定めることができるため、①父母の双方を親権者とするか、父母の一方を親権者とするか、②父母の一方を親権者とするのであれば、いずれを親権者とするかという二段階の審理が必要となる。そして、改正法案は、父母の双方を親権者とするか、その一方を親権者と定めるかは「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」と規定するほか(改正法案819条7項柱書前段)、DV事案等については前記(1)のとおり改正法案819条7項1号2号が判断基準となる。
もっとも、現状、①に関して父母の双方を親権者とするか、父母の一方を親権者とするかの判断基準は、改正法案819条7項1号2号の要件のほかは「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮」するというだけで、明確に示されていない。また、父母の対立を理由に①の段階での一回的な解決ができず、二段階での審理が必要となるケースも想定されるため、審理の長期化が進み、子の利益に反する結果となりうる。
2 親権の行使に関しての問題点
(1) 共同で親権行使が必要な事由・単独で親権行使が可能となる事由が不明確であること
改正法案に基づき離婚後も父母が共同親権者となる場合、「監護及び教育に関する日常の行為」以外の親権の行使については、原則として父母双方の合意が必要となる(改正法案824条の2第1項柱書本文、同条第2項)。しかし、「監護及び教育に関する日常の行為」という文言のみではどのような段階の行為までが「監護及び教育に関する日常の行為」に当たるのかが不明確である。
また、共同親権とされた場合であっても、例外的に単独で親権行使ができる場合として、「子の利益のため急迫の事情があるとき」(改正法案824条の2第1項3号)が定められている。この点、「急迫の事情」とはどのような場合を指すのかについては、法制審議会においては「父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時の親権行使をすることができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるようなケース」をいうとされ、具体的にはDVや虐待が生じた後、子連れ別居を開始する場合も含むという理解が共有された。しかし、「急迫」という文言からこのようなケースを想定することは困難であるし、またその他具体的にどのようなケースで単独での親権行使が認められるかが、親権を行使する父母にとって不明確である。
上記のように、共同での親権行使が必要なのか、単独で親権行使を行ってよいのかといった基準が不明確であると、父母が親権の行使をするにあたって、親権行使の適法性に問題がないかを考えるあまりに、適時適切な親権行使を行うことができず、結果として子に不利益を生じさせる可能性がある。
(2) 共同での親権行使によって適時適切な対応が困難になること
改正法案によると、父母が離婚協議の際に共同親権とすることに合意できなかった場合でも、裁判所が、共同親権を命ずることができる。つまり、離婚する父母が共同で親権を行使すること自体に合意できない状況であるにもかかわらず、裁判所が「共同して親権を行使しなさい」と命じることができるのであり、果たして子の最善の利益になる親権行使が可能であるかの問題がある。このようなケースでは父母は何らかの不和があり離婚していることが多いため、父母双方の合意が必要な事由であることが明確な場合であっても、適時適切な対応を行うことが困難なケースも多いという問題点がある。
協議では合意することができない場合には、さらに家庭裁判所の関与が必要となることも予想される。
しかし、このような紛争が激増すると、家庭裁判所の対応が追いつかなくなる可能性がある。その結果として、適時適切な手続きをすることができず、子に不利益が生じる可能性がある。とりわけ、子に対して医療行為を施すかについて親権者の同意が必要な場合については、医療機関が親権者の同意なく治療を行うリスクを懸念したことで処置ができず、子を命の危険にさらす可能性があるため、重大な問題となりうる。
3 今後求める対応について
上記の問題点は、いずれも結果として子の利益を害するものである。そのため、各機関に対し、以下のとおり、さらなる検討・対応を求める。
(1) まず、参議院での審議においては、以下の点に留意し、さらなる慎重な審議を求める。
1点目として、現状の改正法案における文言が不明確な点及び判断基準が不明確な点について、疑義や紛争を生じさせないように文言自体の変更を含めたさらなる検討を求める。
2点目として、現状の改正法案では、離婚後に父母が共同親権者となった場合に、文言の不明確性や合意ができない等の理由で父母が適切な対応をすることができず、子の利益を害する可能性が高い。そのため、父母が離婚後に共同親権者となった場合に生じうる問題点を把握し、適切な選択ができるよう関係機関が連携して説明やサポートをする制度の構築に向けての検討を求める。
(2) また、国及び関係機関に対しては、以下の対応を求める。
改正法案が成立・施行された場合には、家庭裁判所がこれまで以上に重要な役割を担うことになる。しかし、現在において、家庭裁判所の人的・物的体制は不十分であり、このまま改正法案が施行されても、家庭裁判所が期待される役割を果たすことは困難である。そのため、家庭裁判所の体制の拡充、財源確保が急務であり、改正法案の施行までに実現されるよう求める。
当会は、共同親権の導入に当たっては、子やDV被害者の利益を守ることを十分に配慮すべきであると強く主張し、上記の問題点について、参議院における慎重かつ十分な審議を求めるとともに、家庭裁判所の体制の充実化や関係機関の連携強化を図るよう強く求めるものである。
2024(令和6)年5月14日
鹿児島県弁護士会
会長 山口 政幸