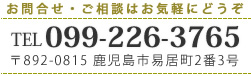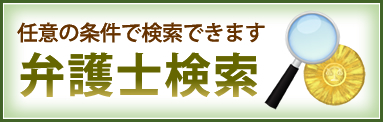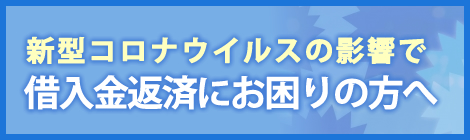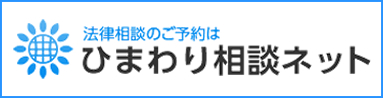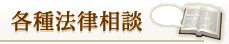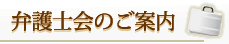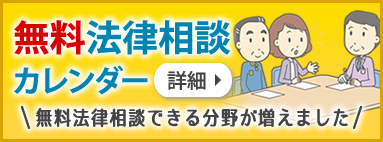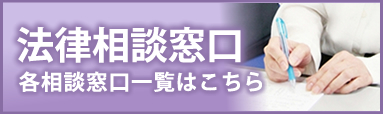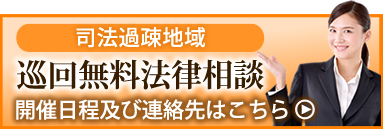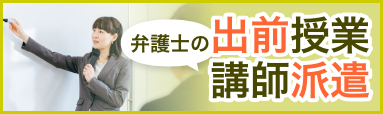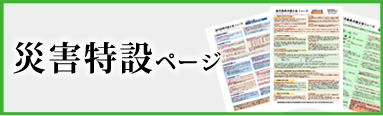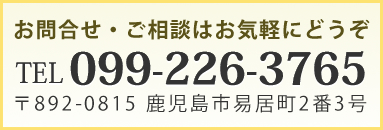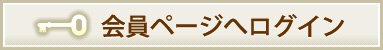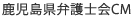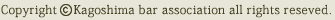決議・声明
死刑制度の廃止を求める決議
決議の趣旨
当会は、政府及び国会に対し、死刑の執行を直ちに停止し、速やかに死刑制度を廃止することを求める。
決議の理由
1 死刑は個人の幸福追求の源となる生命を剥奪する究極の刑罰であること
⑴ 日本国憲法13条は、個人の幸福追求の源となる生命に対する権利(生命権)に対し、最大の尊重を必要とすると規定している。また、世界人権宣言3条は「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する」と規定し、日本が1979(昭和54)年6月に批准した国際人権規約B規約(以下「自由権規約」という。)6条1項も「すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する」「何人も、恣意的にその生命を奪われない」と規定している。
これらの規定は、すべての人は「ただ人である」というだけで当然に基本的人権を有しており、その最も根幹にある人権が「生きる権利」「生命を奪われない権利」という生命権であり、生命権の不可侵を定めている。最高裁判所も「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。」(最高裁判所昭和23年3月12日大法廷判決。以下「昭和23年最高裁判決」という。)と述べている。
⑵ 他方、死刑は「尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るもの」(昭和23年最高裁判決)として刑罰の中で最も苛烈であり、誤判に基づく死刑判決の場合には、ひとたび執行されてしまえばもはや取り返しのつかない、生命の剥奪という重大かつ深刻な結果を招来する刑罰である。
しかし、刑罰制度は、犯罪への応報という考え方のみに由来するものではなく、受刑者の改善・更生により社会全体の安寧に資するものでもある。本年6月に懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑に一本化する改正刑法が施行されたのも「応報を主眼とする刑罰制度」から「更生と教育を主眼とする刑罰制度」への移行を意味するものであるところ、死刑は罪を犯した者の更生を指向しない唯一の刑罰であり、改正刑法の上記理念とは相容れない異質なものと言わざるを得ない。
2 死刑制度には「誤判による無辜の処刑」という最悪の事態をもたらす危険がある上、誤判による死刑執行の可能性は稀有な例外にすぎないとは言い切れないこと
⑴ 無実の者に対し死刑を執行することは、国家による、取り返しのつかない究極の人権侵害であるところ、刑事裁判は人が人を裁くものである以上、誤判・冤罪を完全に排除することは不可能であり、「誤判による無辜の処刑」という国家による究極の人権侵害を絶対的に防止するためには、死刑制度を廃止する以外に手段はない。
⑵ わが国では5件の死刑確定事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件及び袴田事件)において再審無罪が確定しているが、これらの事件は、刑事裁判手続に誤判・冤罪の危険があることを如実に示している。例えば、袴田事件は2024(令和6)年9月26日に再審無罪判決が言い渡され、同年10月9日に無罪が確定したが、1980(昭和55)年に死刑が確定されてからであっても44年の長きにわたって、無実であるにもかかわらず、死刑執行の恐怖に絶えず怯え続けてきた袴田巌氏の心中は想像を絶するものがある。
⑶ しかも、「誤判」の中には、被告人が真犯人か否かという犯人性に関する誤判だけではなく、責任能力の判断場面における誤判や、犯行全体における被告人の役割の評価に関する誤判、さらには被告人に有利な量刑事情が見落とされることに起因する量刑の誤判の可能性もあることから、誤判に基づく死刑執行の可能性は、決して、「稀有な例外にすぎない」とは言い切れない。
3 国際協調主義(98条2項)を定め、国際社会の中で「名誉ある地位を占めたい」と願う日本国憲法の下、日本政府は、人権の尊重、生命権の不可侵を巡る国際的な動向を軽視すべきではないこと
⑴ 昭和23年最高裁判決は、死刑の合憲性につき、憲法は「現在多数の文化国家におけると同様に、刑罰としての死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」と判示したが、2年後の1950(昭和25)年の時点では死刑廃止国は僅か8か国にすぎなかったことから、「現在多数の文化国家におけると同様」という判示も、いちおう当時の判断としては是認し得るといえよう。
⑵ しかし、昭和23年最高裁判決から70年以上が経過した2024(令和6)年末時点においては、死刑廃止国(事実上の廃止国を含む。)は世界の3分の2以上の145か国に及んでおり、OECD(経済協力開発機構)加盟国38か国に限って見れば、死刑制度を存置しているのは韓国、米国、日本のみであるところ、韓国は1997(平成9)年以降死刑を執行していない事実上の廃止国であり、米国も事実上のものを含めて過半数の州で死刑が廃止されており、国家として死刑制度を許容し、死刑を執行しているのは日本だけである。
しかも、国連は、日本も批准している自由権規約6条が死刑の廃止に言及していること(自由権規約は日本国内において法的効力を有している。)を踏まえて、1989(平成元)年に「死刑の廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する国際規約・第二選択議定書」が総会で採択され、2025(令和7)年3月現在締約国は92か国となっているが、日本は批准していない。
⑶ このような国際社会の動きは、人権の尊重、生命権の不可侵という個人の尊厳に関わる価値観が普遍化してきていることに基づくものと解されるが、そのような国際情勢の下、わが国は、国連の国際人権(自由権)規約委員会、拷問禁止委員会による勧告のほか、人権理事会の普遍的定期的審査においても、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討すべきである等の勧告を繰り返し受けており、死刑廃止を迫られている状況にある。
日本国憲法は、前文で「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」と謳っており、98条2項で国際協調主義を定めているが、日本政府や国会は、国際社会の中で「名誉ある地位を占めたい」という前文の願いを真摯に受け止め、上記の国際情勢に視野を広げて死刑廃止問題を真剣に検討すべきであり、人権の尊重、生命権の不可侵を巡る国際的な動向を軽視すべきではない。
4 結論
以上の理由により、当会は、政府及び国会に対し、死刑の執行を直ちに停止し、速やかに死刑制度を廃止することを求めるものである。
2025(令和7)年8月30日
鹿児島県弁護士会
臨時総会決議の内訳
会員数231名
賛成124票 反対22票 棄権2票